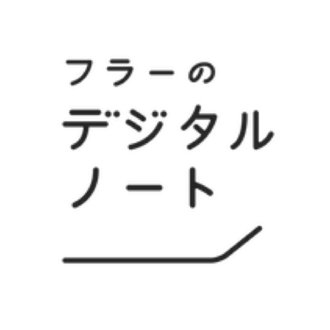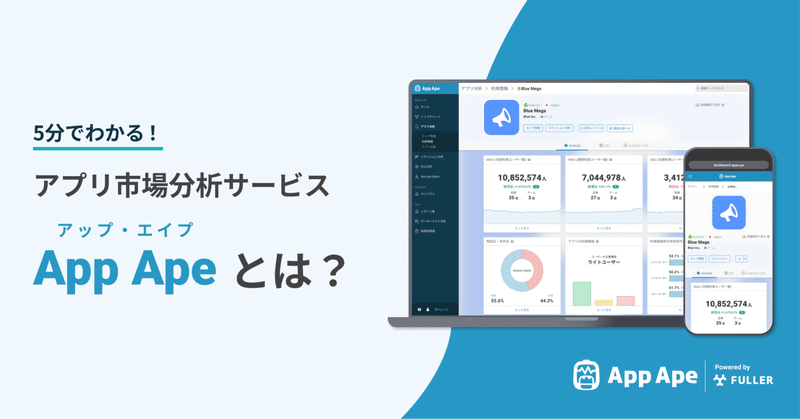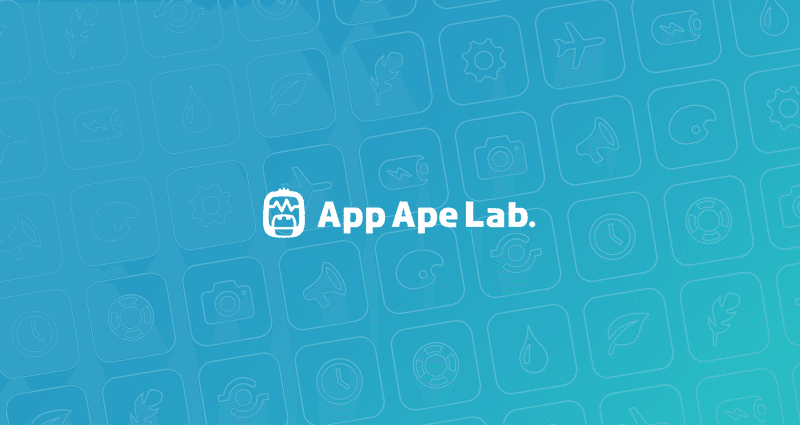
- 運営しているクリエイター
記事一覧

マイクロソフトの生成AIアシスタント「Microsoft Copilot」をビジネスシーンで活かすには? App Ape Award 2023 ネクストスタンダード賞アプリインタビュー
フラーが手がけるアプリ分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」のデータをもとにユーザーに愛されたアプリを選ぶ「App Ape Award 2023」で、「Bing:AI&GPT-4とチャット」が「ネクストスタンダード賞」に選定されました。 生成AIアシスタント「Microsoft Copilot」を機能として組み込んだ「Bing:AI&GPT-4とチャット」のアプリとしての魅力やCopilotのビジネスでの生かし方について、マイクロソフトディベロップメント株式会社W
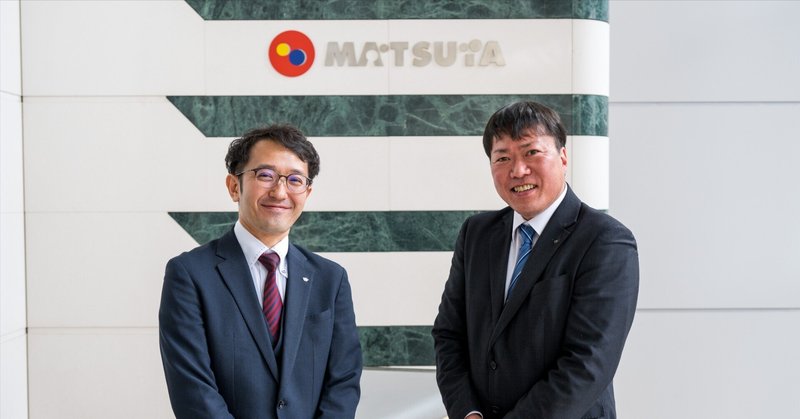
お客様を“儲けさせる” 松屋フーズ公式アプリに込める思いとは App Ape Award 2023 リテール賞アプリインタビュー
フラーが手がけるアプリ分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」のデータをもとにユーザーに愛されたアプリを選ぶ「App Ape Award 2023」で、「松屋フーズ公式アプリ」が「リテール賞」に選定されました。 「松屋フーズ公式アプリ」が辿ってきたアプリとしての成長の軌跡や注力した施策・取り組みについて、アプリを運営する株式会社松屋フーズの小曽戸チーフマネジャーと大野マネジャーに伺いました。(敬称略、記事:石徹白未亜、編集:日影耕造、写真:島、日影) 松屋フーズ公

アプリはchocoZAPに欠かせない“インフラ” 革新的なジム&宅トレアプリはいかにして生まれたのか App Ape Award 2023 DX賞アプリインタビュー
フラーが手がけるアプリ市場分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」のデータをもとにユーザーに愛されたアプリを選ぶ「App Ape Award 2023」で、「chocoZAP(チョコザップ)ジム&宅トレアプリ」が「DX賞」に選定されました。 店舗数 1333店、会員数112.4万人(2024年2月14日時点)と躍進を遂げる24時間無人運営のコンビニジム「chocoZAP」。この仕組みを支える「chocoZAPジム&宅トレアプリ」の成長の軌跡や取り組みについて、RIZ

[2023年版:SNSアプリのユーザー層や使い方の違い]X(旧Twitter)・Threads・TikTok・Instagram・Facebook・LINEを比較
マーケティングやブランディング、情報共有など生活やビジネスシーンにおいて欠かせないツールとなったSNS。SNSアプリの動向を知ることは、世の中の動きや現状、ビジネス戦略や具体的アクションを考える上で重要な要素と言えます。 Twitterの名称変更や新たなアプリのローンチなど、大きな変化の最中にあるSNSアプリ。ユーザー層やアプリの使い方はどんな状況になっているのでしょうか? SNSアプリのユーザー層と使い方をアプリ分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」のデータ